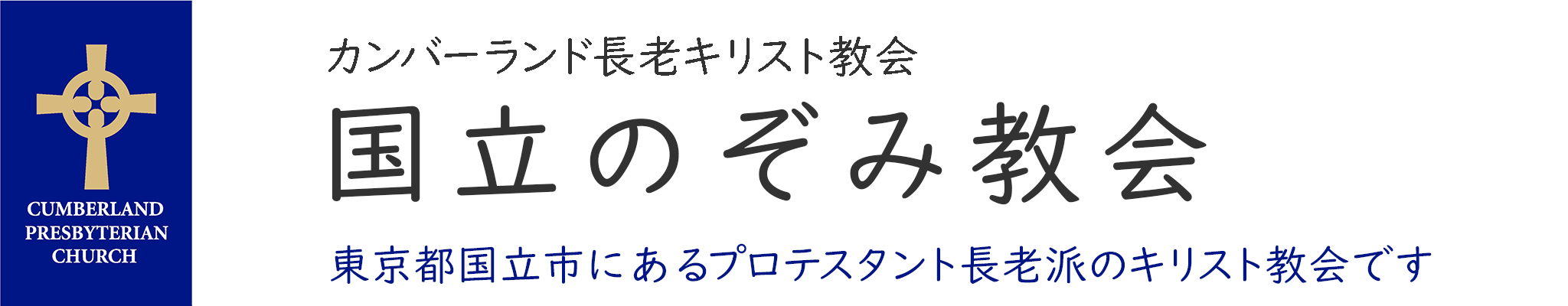イエスが語られた「この最も小さな者の一人にしたのは、私にしたのである」という言葉は、マタイによる福音書にのみ記されたものであり、しかもイエスが地上で弟子たちに語った最後の説教の一節である。その重みは、単なる道徳的教えではなく、終末を見据えた主のまなざしと深くつながっている。ここに登場する「最も小さな者たち」とは、飢え、渇き、宿を持たず、裸で、病み、牢に囚われている人々のことである。衣食住の不安、健康の喪失、自由の剥奪——それは今の世界においてもまさに現実の問題であり、主はそれらを担う者の中にご自身を重ねられたのだ。
ミャンマーの地震、パレスチナやウクライナでの戦争、難民や虐待される子どもたちの声は、まさに「最も小さな者たち」の叫びであり、それはイエスご自身の叫びでもある。しかし私たちは、目の前の現実に無力感を覚える。衣食住が整った日本に生きる私には、世界の飢えに実感を持つことが難しい。そして、何もしていないという負い目がある。映画『ホテル・ルワンダ』で語られる「人々は映像を見て“怖いね”と言ってディナーを続ける」という言葉は、まさに自分への言葉として刺さってくる。
そんなとき思い出すのが、20年前のある出来事である。駆け出しの伝道師として赴任して間もない頃、助けを求めて教会に来た家族を、私は泊めることができなかった。未熟児で生まれた娘が退院したばかりで、自分の生活の余裕もなかった。だが帰り道、大学通りを運転しながら、「イエス様だったらどうしよう?」という思いが胸を突き刺した。その家族は、私にとって今も迎え損ねた“聖家族”として記憶に残っている。
主イエスは、私たちが右か左かを分けられるためにこの言葉を語ったのではない。むしろ、ペトロが裏切り逃げてしまうことを知っていたように、弱い者たちにこそ宣教を託し、再び立ち上がるよう呼びかけておられるのだ。いまこの地に響く「イエスの叫び」に対して、私たちはどうしたらいいかわからずにオロオロする。しかしそのオロオロこそが、無関心から抜け出す第一歩なのである。神はそのオロオロのただ中におられ、共に泣き、叫び、そして招いておられる。
私たちはすべての痛みに応えられないし、すべての叫びに届くことはできない。けれど、一人の声に耳を傾けることはできる。主はその小さな愛を「わたしにしてくれた」と言ってくださるお方だ。たとえ自分で覚えていなくても、主は覚えていてくださる。
だからこそ、私たちは今週も目の前のひとりに仕えたいと思う。そして、自らが「最も小さな者」と感じられる日が来たときにも、主が「私はここにいる」と言ってくださることを信じて歩み出したい。主は、いま、私たちに出会うお方である。
〒186-0002
東京都国立市東3-15-9
TEL&FAX 042-572-7616