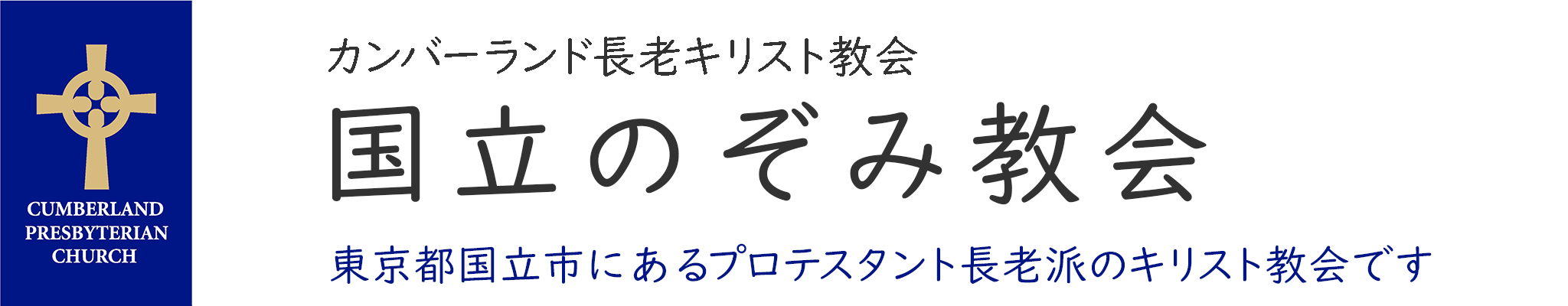モーセは120歳でその生涯を終えた。波乱万丈に満ちた人生であった。80歳でエジプトの奴隷であったイスラエルの民を脱出させるようにと神に召し出された。40年間、民に不平不満を言われながらも荒野を旅し、約束の地を目指して旅を続けた。
ところが神は、約束の地を目の前にしながらモーセに告げる。「私はあなたにこの地を見せるが、あなたはそこへ渡っていくことはできない。」モーセはネボ山の頂に登り、北から南まで神が与える地を一望したが、自らその地を踏むことは許されなかった。その原因は民数記20章に記される「メリバの水事件」にある。神に命じられた通りに岩に語りかける代わりに、モーセは岩を杖で二度打った。それが神の聖を現さなかったとされ、約束の地への入場を禁じられたのだ。
わずかな過ちで人生の夢が閉ざされる。理不尽に思えるが、モーセは運命を受け入れた。申命記3章では、モーセが神に「どうか渡らせてください」と嘆願する場面があるが、神は「もう十分だ。このことを二度と語るな」と退ける。それでもモーセは目を曇らせることなく、後継者ヨシュアを励まし、最後まで与えられた道を歩んだ。
申命記34章7節はこう記す。「モーセは死んだとき、百二十歳であったが、目はかすまず、気力も失せていなかった。」これは単なる老眼の話ではない。神の示すものを見続け、使命を見失わず、最後まで走り抜いたという意味である。
人は皆、未完成のまま終わりを迎える。やり残したことや後悔を抱えながら、それでも与えられた一日一日を生き抜くのだ。ヴィクトール・フランクルは『夜と霧』の中で語った。「人生の意味を問うのではなく、人生から問われているのだ」と。ナチスの強制収容所という極限状況の中で、生きることから「何をするよう求められているのか」と問うたフランクルの言葉は、モーセの生き方とも重なる。約束の地に入ることはできなかったが、モーセは「見るべきものを見続ける」生涯を貫いたのだ。
先日のサマーキャンプでTさんが子どもたちに、自身の座右の聖句としてピリピ3章13-14節を紹介した。「後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、キリスト・イエスにあって神の賞を得るために、目標を目指してひたすら走る」。彼は洗礼を受けて「人生の目標が変わった」と語った。仕事や学校の目標も大切だが、神から与えられる賞を目指す生き方に変えられたと告白したのだ。信仰に生きるとは、命の使い方が変わるということである。
申命記は「イスラエルには、再びモーセのような預言者は現れなかった」と結ぶ。しかし私たちは知っている。モーセを超える方、主イエス・キリストが来られたことを。イエスは「時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」と告げられた。その十字架と復活によって、神の国の景色を私たちに示されたのだ。
礼拝とは、モーセがピスガの頂から約束の地を見たように、神の国の景色を見つめる場所である。争いや分断、罪に満ちた世界のただ中で、私たちは主イエスを通して「愛と義が支配する神の国」を先取りする。この景色を見つつ、生き方を定め、命を使う。
人生には始まりがあり、終わりがある。しかし、終わりは神の国への扉であり、私たちはそのビジョンを見つめて生きる。モーセがピスガの頂から見た景色を胸に刻み、主イエスによって示された神の国を望み見ながら、私たちは命を使い切る道を歩むのである。
動画はこちら⬇️