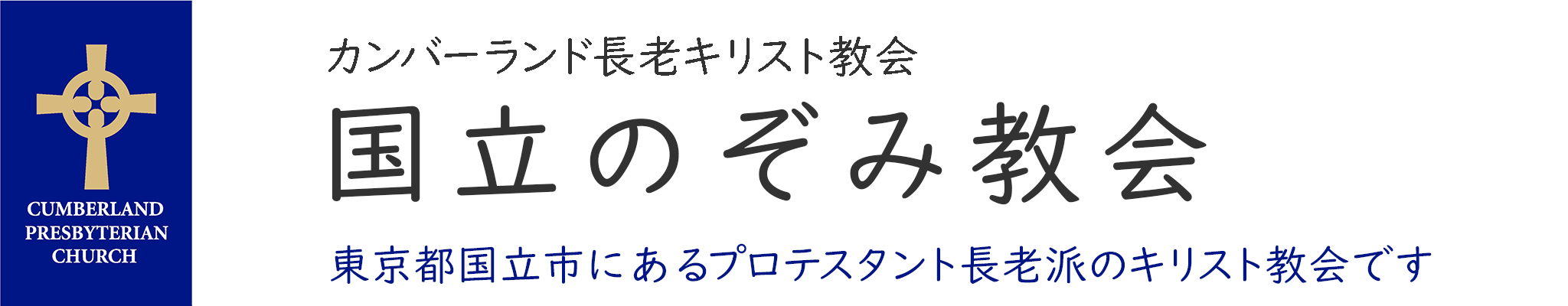パウロは、コリントの信徒たちに宛てた手紙を読んでも分かる通り、大変苦労しながら、文字通りに命がけでキリストの福音を宣べ伝えた人だ。そのパウロが、福音宣教と並んで、各教会を回りながら熱心に取り組んだもう一つのことがあった。それはエルサレム教会のために献金を集めるということだった。エルサレム教会の兄弟姉妹たちの困窮を支えることは、パウロにとって「一つの体なる教会」として重要な意味を持つことだった。ユダヤ人教会と異邦人教会の間にある種の緊張がある中で、献金という行為が「一つの体」であることを具体的に証しする業として、パウロは大事にし、熱心に各教会に呼びかけた。
しかしコリント教会においてパウロとの関係悪化も影響したのであろう、エルサレムへの献金活動が頓挫してしまっていた。「なぜ私たちがエルサレム教会を支援しなければいけないのか、そんな余裕はない」という反発もあったと言われる。
そのことを受けてパウロは、それではマケドニアから兄弟たちが到着した時に、あなたがたも、コリント教会のことを誇らしく語ったわたしたちも献金の準備ができていないとなると、「恥をかくことになりかねません」という。「恥」の感情に訴えかけるなど非常に人間くさく、赤裸々な訴え方だが、それほどまでにエルサレム教会への献金をパウロは重要視していたということだろう。
そこでパウロは当時のよく知られた格言を引用しながら語る。「惜しんで僅かに蒔くものは、僅かに刈り取り、豊かに蒔く者は、豊かに刈り取るのです」(6節)。教会の働きを語るときの種の大胆さ、ダイナミックさを語る格言として受け止めたい。教会の献金や教会での「金勘定」をする時に忘れてはいけないことだ。パウロは「神はあらゆる恵みをあなたがたに満ち溢れさせることがおできになります」(8節)と続けて語る。だからこそ、大胆に、豊かに蒔くことができるのだ。この神へ信頼を失ってしまうと、私たちは「現実」だけに心を奪われてしまう。私たちの教会の現実は、各個教会も、中会も、日本の諸教会においても、前途洋々ではない。現実を無視してよいということではない。しかし、現実を凌駕する神への信頼を失ってはならない。献げるという行為は、神を信頼する現れにほかならない。
「献げる」ということは、私たちの頭で理解するのではなくて、身をもって経験することなのだ。山の本を読んでも、山を理解することができないように、「献げる」ということも実際に一歩を踏み出して自分たちの計算を超えたところでささげ、その働きに応答しなければ、理解できない。
パウロの言葉は、一歩間違えるとご利益宗教でも使われそうだ。しかし、パウロは、多くの種を蒔いて、自分たちが肥大化していく。拡大していく、そのようないう意味で、「刈り入れ」を語っているのではない。「この奉仕の業は、……神への多くの感謝で満ち溢れるものになるからです」(11節)。豊かに蒔く者が刈り入れるのは神への感謝なのである。献げるからこそ味わい知る神への感謝がある。
「各自、いやいやながらではく、強いられてでもなく、心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は祝してくださるからです」(7節)。