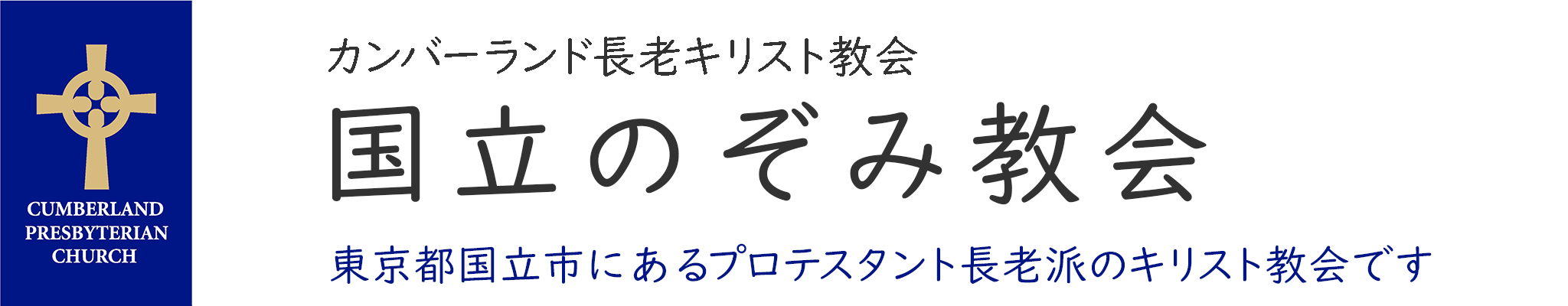民数記は、モーセ五書のひとつであり、エジプトを脱出した神の民が約束の地を目指して荒野を旅する姿を描いている書である。もともとのヘブライ語の表題は「荒野において」という意味だ。この書は、神の民が荒野で試練の中を旅し、神の導きによってアイデンティティを形づくられていく物語である。
特に印象的なのは、神の民の旅が神の臨在のしるしである「雲」の動きに従っていたということだ。雲が幕屋の上にとどまっていれば宿営し、雲が上れば進んだ。昼夜を問わず、雲の動き次第で旅が決まる。どれほどとどまるのか、いつ進むのかは人間の計画にはなく、ただ神の命令に委ねられていたのである。私はこの旅を想像すると、不安と苛立ちを覚える。できるだけ早く目的地に着きたいと願う性分だからだ。雲の動きのタイミングも法則性がなく、何日とどまるのか予告もない。ただ神の命令によって進み、止まる。それは、人の目には非効率で、まどろっこしく、時に愚かにさえ見える道のりである。
しかし、ここに神の民の歩き方の本質が示されている。神の時を捉え、その命令に従うことこそ、神の民の旅の流儀なのである。イザヤ書の言葉の通り、神の思いと人の思いは異なり、神の道は人の道よりも高い。神は時に近道ではなく遠回りを、時に思いがけない長い滞在を命じられる。それでも神は民を見捨てず、約束の地へと導かれる。
この荒野の旅は、私たちキリスト者の歩みにも重なる。私たちは地理的な約束の地ではなく、神の国を目指して旅をしている者たちである。ペトロの手紙1に「あなたがたはこの世では寄留者であり、滞在者なのですから」(Ⅰペトロ2:11)とあるように、私たちはこの地上にあって旅人であり、仮住まいの者である。教会の歩みも同様で、神の国を目指す途中の群れ、つまり荒野の教会なのである。
その旅は人間の計画通りにはいかない。宣教方針や教会の将来計画を祈り考え、見通しを立てようとするが、神の導きはしばしばその枠を超える。分断と対立が深まる世、平和が脅かされ、社会の高齢化が進む現実に、私たちは未来への不安を抱く。しかし、民数記の物語が語るように、神の民は「主の命に従う」ことに集中すべきである。神の時に従い、神のペースに歩むことこそが、旅の本質なのである。
先月はパウロの記したフィリピ書を読んだが、パウロもまた、自分の思い通りではない道を歩まされた。使徒言行録には、アジア州で宣教しようとしたが「聖霊から禁じられ」、ビティニアにも行けず、結局トロアスから海を渡りマケドニアに向かったと記されている。神の導きは、パウロ自身の計画とは異なるものであったが、その結果、福音はヨーロッパへと広がった。神の計画と人の計画は異なるのである。
今の時代もまた、私たちは現代の荒野を旅している。不安と恐れが満ち、見通しのきかない社会にあって、潤いを失った不寛容な世界に生きている。そんな中で、神の命に従って歩むことが求められている。荒野の雲が神の民を導いたように、神はイエス・キリストという目に見える御方をこの世に遣わされた。イエスは良き羊飼い、命のパン、命の水として、私たちの旅を導いてくださる。このイエスの御言葉に聞き従い、神を愛し、隣人を愛することが、私たちの旅の道しるべである。